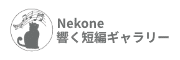【短編小説全10話】第1話:鳴かない朝
1.
目覚ましが鳴るより早く目が覚めた。
理由は分かっている、理由がもうないことも分かっている。
いつもなら、胸の上か腹のあたりか、あるいは枕の横
どこかに小さな重みがあった。毛の温度、呼吸のリズム、喉の奥で小さく回るエンジンみたいなゴロゴロ、起きろと命令するでもなく、ただ「朝だよ」と生活の形だけを整えてくれる重み
今朝は、それがない。
天井の白がいつもより冷たく見えた。部屋の空気は同じはずなのに、輪郭だけが鋭くて、触れたら指が切れそうな気がする。
私は息を吸って、吐いた。
それだけで一日が始まってしまうのが怖かった。
2.
身体を起こして布団をめくる。足の裏を床につける瞬間、反射的に力を抜いた。寝ぼけたまま踏まないようにいつも、そこに柔らかいものが転がっている可能性があったからだ。目が合ったら「ごめん」と言いながらそっと跨いで、ハルが不満そうに目を細めても、結局は私の足元に絡みつく。
今は、床がただの床。
「……ごめん」
誰もいない床に言葉が落ちる。謝る相手がいないのに謝ってしまう
謝る癖だけが、まだ生きている。
3.
カーテンを少しだけ開けた。薄い冬の光が窓枠に沿って部屋へ流れ込む。外は灰色で、昨夜の雨がまだ残っているみたいだった。雨の匂いはしない、代わりに濡れたアスファルトの匂いが空気の底に薄く沈んでいる。
窓辺には小さな毛布が畳んで置いてある。ハルの指定席だった。
日当たりがよくて、午後になるとそこだけ少し暖かくなる。ハルはそこで丸くなって、あくびをして、尻尾の先をゆっくり動かしていた。
窓の外を眺めるわけでもない。眺めているように見えるだけで、たぶん何も考えていない
考えていないことが、こちらには救いだった。
今日は、毛布が「物」になっていた。
ハルがいる時は「場所」だったのに。
触ろうとして、やめた。触ったら何かが崩れそうで
代わりに視線を逸らし、台所へ向かう。
4.
廊下を歩く足音がやけに大きい。ハルがいた頃は足音の合間に爪の音が混ざった。カツ、カツ、カツ
木の床の上を少しだけ急いで追いかけてくる音。私が台所へ向かうと、ハルも一緒に来るのが当たり前だった。
今は私の足音だけ。
それが、間違っているみたいに響いた。
台所の照明を点ける。蛍光灯の白い光が鍋の縁やシンクの水滴に反射して目に刺さる。湯を沸かすためにポットを手に取り、蛇口をひねった。水が流れる音がする
その音が、まるで「何も変わっていない」と主張しているようで腹の奥がムズムズした。
ハルは水の音が苦手だった。蛇口の水を見て少し距離を取って、眉間を寄せるように目を細める。水滴が飛ぶとさっと後ろへ下がって、それでも興味はあるからまた少し近づく
見守る私の方をチラッと見て、「大丈夫?」とでも言うように首を傾げる。大丈夫じゃないのは、いつも私の方。
ポットに水を入れてスイッチを押す。カチ、と小さな音。
それだけで私は立ち尽くした。
何をすればいいのか分からない。
正確に言えば、するべきことは分かっている。朝ごはん、洗濯、仕事、メールの返信
生活のタスクは山ほどある、でもその全部がハルの存在を前提に組まれていた。
5.
ハルのごはんを用意して、トイレを掃除して、窓を少し開けて換気して。
外出する時は空調を調整して、カーテンを半分だけ閉めて。
帰ったらまずハルの姿を探して、名前を呼んで、返事がなければちょっと不安になって、やがて「ここか」と見つけて安心する。
その一連が生活の「骨」だった。
骨が抜けた生活は、ただの柔らかい塊で形を保てない。
冷蔵庫を開ける。中の光が白い。
牛乳、卵、納豆、作り置きの味噌汁
ハルがいた頃と変わらないはずの中身が、変わって見えた。
変わったのは私の方。
下段に小さなタッパーがある。ハルの薬を入れていた。飲ませるのに苦労した
粉薬をウェットに混ぜると気づかれる。ほんの少しでも匂いが違うと、舌先で確かめるようにして食べるのをやめる
仕方なくシリンジで水に溶いて、口の端から少しずつ入れる。
ハルは毎回、目を細めて不満そうにして、それでも最後には諦めて飲んだ。飲んだあと、ちょっとだけ距離を取る
抗議のつもりなのか、ただのルーティンなのか。私は「ごめんね」と言ってハルの喉を撫でた。撫でると、ゴロゴロが少し早まることがあった。
タッパーを見て、冷蔵庫を閉めた。
今朝は、何も食べたくない。
6.
居間へ戻る。床の上に爪とぎがある。段ボールの、少し削れたやつ
ハルが最後に使った時の爪跡が残っている。片付けようとして、途中で止めた。片付けてしまったら、いなくなったことが確定してしまうような気がした
確定しているのに。
ソファの端が少しほつれている。ハルがよくそこを狙って爪を立てた。私が「こら」と言うと、ハルは悪びれもせず目を細めて伸びをする
伸びの途中で爪が引っかかって、慌てたように後ろ脚を振って、結局そのまま座り直す。
その間抜けさがいちいち可愛かった。
「可愛い」という言葉は、生活の中で少しずつ増えていって、いつの間にか私の語彙を占領していた。
スマホを見る。通知が溜まっている。仕事のメッセージ、確認事項、今日の予定
画面の文字は読めるのに意味が頭に入ってこない。指でスクロールして止めて、またスクロールする
機械的な動きだけが続いた。
7.
その時、「カツ」と音がした気がした。ほんの一瞬
床のどこかで小さな爪が鳴ったみたいな。
息を止める。耳が痛くなるほど静か。
もちろん何も聞こえない。
たぶんポットの沸く音の錯覚か、冷蔵庫が鳴ったか、隣の家の何かが響いただけ
そういうふうに説明できる。
でも、説明がつくことと心が納得することは別だ。
私はハルの名前を呼びそうになった。喉の奥まで音が上がってきて、口を開く
そこまでして、ようやく思い出す。呼んだら戻ってこない。
口を閉じる。舌が乾いていた。
鳴かない朝だ。
ハルが鳴かない朝なんて、これまでにもあった。ハルはよく鳴くタイプではなかったし、返事もしない日があった
名前を呼んでも、しっぽだけ動かして、目を半分開けて「うるさいな」と言いたげな顔をする。
だから鳴かないこと自体は珍しくない。
でも今日は違う。
鳴けない朝だ。
8.
私は立ち上がり、トイレがあった場所を見る。
もう、ない。昨日片付けた。袋に入れて、ゴミの日まで玄関に置いてある
部屋に残しておく勇気がなかった。臭いが残るのが嫌だったのではない、臭いが消えるのが怖かった。
玄関の方を見る。靴が揃っている。ハルの毛がついたままのコートがハンガーにかかっている
その毛が、まるでハル自身の「在席確認」みたいに思えて、一瞬だけ安堵する。安堵してしまった自分に、すぐ嫌気がさした。
私は変だ。普通じゃない。
そう思った瞬間、胸がきゅっと縮んで呼吸が浅くなる。
喪失は、涙より先に身体を壊してくる。
そのまま床に座り込む。背中をソファに預ける。ソファの布の匂いがする
そこに混ざっているはずのハルの匂いが、もう薄い。
薄いことに気づいてしまったことが、なぜか罪みたいに感じた。
目が勝手に濡れてくる。泣くというより、身体の余計な水分が漏れ出してくる感じ
手の甲で目元を拭いて、息を吸って吐く。
吸って、吐いて。
それだけで胸の奥に小さな穴が開いていく。
9.
昨日のことを思い出さないようにしようとすると、思い出してしまう。思い出さない努力は、思い出す作業そのものだった。
病院へ行ったのは夜が明ける前。外はまだ暗く、街灯の光が濡れた道路に滲んでいた
タクシーの窓に雨粒が細かく叩きつけられて、私の呼吸に合わせて曇る。キャリーの中でハルは静かだった
静かすぎて、何度も指を差し入れて毛に触れた。温かい。そこだけが現実。
待合室は暖房が効きすぎていて、消毒の匂いが濃い。床はやけに清潔で、壁のポスターの犬や猫の笑顔が、今日に限っては別の世界のものに見えた。
受付の人は丁寧で、医師は落ち着いていて、それが怖かった。落ち着いている人は結末を知っている顔をしている
勝手に、そう思った。
診察室の金属の台にハルを乗せる。ハルは小さく身を縮めた。抵抗はしない
ただ目だけが、いつもより大きく開いていた。
私は「大丈夫」と言ってしまう。何が大丈夫なのか分からないのに。
医師の言葉は優しくて正確。優しい正確さは刃物に似ている。
私はそれを受け取って理解して頷いて、その場では泣かなかった
泣くタイミングを失っていた。
ハルの呼吸が薄くなっていくのを見ていた。見るしかなかった。
終わったあと、毛を撫でた。ゴロゴロは鳴らなかった
鳴らなかった、というより鳴らせなかった。
「ごめんね」
それしか言えなかった。
帰り道、キャリーは軽かった。軽いことに驚いて、すぐ自分が嫌になる。
軽いのは当たり前。ハルはもう力を入れない、体が緊張しない、息がない
だから軽い。
頭では理解しているのに、身体が追いつかない。
10.
家に着いて、キャリーを玄関に置く。靴を脱いで、キャリーを抱えたまま居間に入る
いつもなら、ここでハルが出てくるはずだった。キャリーの中の自分を見て、鼻を鳴らすはずだった。
でも、キャリーの中にいるのはハル。
ハルを毛布に包んで、窓辺に置いた。
置いてしまった。
置いたらそれで終わりになるみたいで怖かったのに置いた。置かないと次の動きができなかった。
昨日の私は、昨日の私のまま止まっている。
今日の私だけが、勝手に動いている。
11.
ポットが沸く音。ピーピー、と短い電子音
毎日聞いてきた音なのに、今日は「これでもう戻れないよ」と告げられているみたいだった。
カップを出し、湯を注ぐ。湯気が立ち上り白く揺れる。
コーヒーを入れる気力はないから、ただのお湯。
それでも湯気があるだけで部屋が少し柔らかくなる。柔らかくなって、余計に寂しい。
窓辺に近づく。毛布の上の空席が目に入る。
目を逸らす。逸らすのに、逸らしきれない。
窓の外に小さな鳥が降りた。雨上がりの電線にとまり、首を振って水滴を飛ばす。
ハルなら見ただろうか。
ハルは鳥が好きだった。正確には「好き」というより、鳥を見ている時だけ顔が少し変わった
目が細くなって、耳が前に寄って、口元がほんの少し動く。カカカ、と喉の奥を鳴らすこともあった。
狩りの本能。
でも狩りはしない。窓の内側で、ただ見ている。
鳥は羽を少しだけ膨らませてから飛び立った。
飛び立つ瞬間、なぜか「行かないで」と思った。
鳥に向けた言葉ではない。分かっている。
分かっているのに、心は勝手。
12.
リビングの棚を開ける。ハルの首輪がある。外して置いたままの薄い布の首輪
鈴はついていない。鈴はハルが嫌がった。小さな音でも敏感だった。
首輪は、ハルが家に来た頃に買った。あの頃のハルは今よりずっと小さくて、毛がふわふわしていて、目が大きくて、世界の全部が怖いみたいな顔をしていた。
私も世界の全部が怖かった。だからハルの怖さが分かった気がした。
首輪を手に取る。布の端が少し擦れている。そこにハルの毛が一本、絡んでいる。
その毛を指でつまみ、落とさないように掌に乗せた。
落としたら終わりになる気がした。
終わりは、もう来ている。
それでも私は「終わり」の端っこに指をかけて、離せずにいた。
13.
スマホが震える。仕事の連絡。短い確認事項、返事をすれば済む。
画面を見て文字を打とうとして、止まる。
指先が動かない。動かないのに胸の奥だけが騒がしい。
どうして、みんな普通に生きているんだろう。
どうして、今日は昨日の続きなんだろう。
どうして、ハルだけいないんだろう。
答えのない問いが頭の中で渦を巻く。
スマホを伏せた。返信しない罪悪感より、返信する現実感の方が重かった。
床に落ちている小さな毛玉に目が止まる。ハルの毛。
掃除機をかければ消える。でも消したくない。消したくないのに、いつか消える
それが怖い。
掃除機のコードが絡まっているのを思い出す。ハルは掃除機が嫌いだった。スイッチを入れると一瞬で逃げて、ソファの裏に潜った
潜って、出てこない。
止めても、しばらく出てこない。出てこないくせに、止めた音だけは聞いている。
「もう大丈夫だよ」と言うと、ゆっくり顔を出す。顔を出して、目だけで私を責める。
「もう大丈夫だよ」
その言葉が今日の私には一番言いにくい。
14.
棚の奥から、ハルの写真が入った小さなアルバムを引っ張り出す。紙の表紙が少し反っている
何度も開いたからだ。
開くと、ハルがいる。
いる、と言える。写真の中では確かにいる。
最初のページは家に来たばかりの頃。小さな段ボール箱の中からこちらを見ている
目は琥珀色でも宝石みたいでもない。ただの、少し怯えた瞳。
その怯えが懐かしい。怯えが懐かしいなんて、思う日が来るとは思わなかった。
次の写真は窓辺で寝ているハル。前脚が伸びて肉球が見えている。肉球はピンクではなく少し黒っぽい。
その肉球に何度もキスをした。ハルは嫌がった。嫌がって、でも逃げない
逃げないから、やめられない。
ページをめくる。キャットタワーの一番上、得意げな顔だけ。段ボールに無理やり入っている写真。洗濯物の上でぬくぬくしている写真。膝の上で寝落ちして、口が少し開いている写真。
その全部が昨日までの私の生活。
アルバムを閉じると、部屋が一気に現実に戻った。現実は写真みたいに固定されない
固定されないから怖い。
15.
立ち上がって、ハルの器が置いてあった場所へ行った。
器は、まだ出したままだ。
昨日、洗って、乾かして、そのまま。
片付ければいいのに、片付けられない。
触れると、陶器の冷たさが指に伝わる。
ハルの舌の温度が、もう乗らない冷たさ。
私は器を持ち上げ、棚にしまおうとして、やめた。
代わりに、テーブルの上へ置く。
棚にしまうのは「片付け」だ。
テーブルに置くのは「置いてあるだけ」だ。
言い訳が、今日も役に立つ。
16.
玄関の方から、ビニールの擦れる音がした。
風だ。玄関に置いた袋が揺れただけ。
袋の中には、トイレ一式と、使いかけの猫砂が入っている。
それらが玄関で待っている、という言い方が気持ち悪い。
物が待つはずがない。
それでも私の中で、それらは
「まだ終わっていない証拠」として存在していた。
袋に触れた瞬間、胸の奥がきゅっと縮んだ。
こんなものに、と思う。
でも、苦しくなるのは袋じゃない。
袋に入れた瞬間の、昨日の自分だ。
震えながら袋を縛った自分。
意味はないのに、結び目を二重にした自分。
「もう、これでいい」
そう言い聞かせるみたいに。
17.
玄関の鏡に、自分が映った。
目が腫れている。頬が少しこけている。髪が乱れている。
別人みたいだと思う。
別人なら、よかった。
別人なら、ハルのいない朝を迎えなくて済む。
でも、鏡の中の人間は私だ。
逃げられない。
今日も、ここにいる。
18.
部屋へ戻る途中、クローゼットの扉が少し開いていることに気づいた。
ハルはよく、そこに入りたがった。
暗くて、狭くて、布の匂いが濃い場所。
閉めても、いつの間にかこじ開ける。
私が閉める。ハルが開ける。
その繰り返しが、何年も続いた。
私は「またか」と言いながら、内心では少し嬉しかった。
誰かが家の中で、勝手にルールを作っている。
それが、生活だった。
扉を閉めようとして、やめた。
閉めたら、もうハルは開けない。
開けない扉は、ただの扉だ。
ただの扉に、したくない。
結局、扉は少し開いたままになった。
19.
スマホが震えた。
知人からの短いメッセージ。「大丈夫?」
その一言を見て、指が止まる。
大丈夫、の範囲が分からない。
大丈夫じゃないと言うには、説明が長すぎる。
大丈夫だと言うには、嘘が大きすぎる。
私は画面を閉じた。
返事をしない罪悪感より、返事をする現実感の方が重かった。
20.
窓辺へ戻る。
毛布は、そのままだ。
日が少し差してきて、毛布の一部が明るくなる。
光のせいで、そこに誰もいないことが、余計にはっきりする。
私は毛布の端を、ほんの少しだけ直した。
直すとき、手が震えた。
戻らないと分かっているのに、直す。
直すことでしか、
今の私は「ハルを扱う」ことができない。
21.
時計を見る。
まだ朝だ。
朝がこんなに長いなんて、知らなかった。
ハルがいた頃の朝は、短かった。
短いというより、分割されていた。
ごはん。
トイレ。
窓。
抱っこ。
ひと鳴き。
背中を撫でる。
小さなタスクの集合体。
今はそれが消えて、時間が一枚板になっている。
逃げ場がない。
22.
湯を飲む。
熱い。痛い。
その痛みが、少しだけありがたい。
身体に感覚が戻る。
感覚が戻ると、思い出してしまう。
23.
ハルの最後の数日。
食欲が落ちた日。
匂いだけ嗅いで、やめたカリカリ。
ほんの少し舐めたウェット。
その「少し」を見て、私は喜んでしまった。
少ししか食べないのに。
少ししか食べられないのに。
「食べた」という事実に、縋った。
24.
水を飲む回数が減った。
トイレに行く回数も減った。
寝ている時間が増えた。
それでも、ハルはたまに顔を上げた。
怯えても、怒ってもいなかった。
ただ、静かだった。
静かすぎて、怖かった。
25.
「様子を見ましょう」
その言葉が嫌いになった。
様子を見ている間にも、時間は進む。
進むことが、怖い。
26.
私はただ、ハルの様子を見た。
呼吸の回数を数えた。
数えながら、喉が乾いた。
乾きながら、眠った。
目が覚めたら、また数えた。
27.
昨日の朝、ハルは私の指を舐めた。
舐めたというより、触れた。
舌のざらつき。
一瞬だけ。
それを、ずっと覚えている。
28.
ハルの身体は、軽くなっていた。
抱っこすると、いつもの重みがない。
重みがないのに、
抱っこの姿勢だけは昔と同じで、
腕が空振りするみたいだった。
癖は、残る。
残る癖が、痛い。
29.
部屋の中に、ハルの影がある気がする。
角を曲がった先。
ソファの陰。
ドアの向こう。
影は、どこにでも作れる。
ハルがいたから、影の形がハルに見える。
30.
探すように歩いていることに気づいて、歩くのをやめた。
探す相手はいない。
探す癖だけが、残っている。
31.
窓の外で、車の音がする。
遠くの道路を走る音。
その音に紛れて、自分の息の音を聞いた。
頼りない。
ハルの呼吸の方が、ずっと確かだった。
32.
確かなものが、もうない。
確かなものは、自分の身体だけ。
その身体は、今、信用できない。
33.
窓の外で、どこかの猫が一度だけ鳴いた。
遠くて、はっきりしない。
でも、猫の声だった。
その声を聞いて、胸が少しだけ揺れた。
34.
世界のどこかで、まだ猫は鳴いている。
その声を聞いて、私は今日を生きる。
35.
ハルが鳴かない朝に、私はひとつだけ約束を作った。
ハルの名前を、消さない。
悲しみを、急いで片付けない。
でも、生活も、捨てない。
矛盾している。
矛盾しているからこそ、今の私に近い。
36.(結)
部屋は同じだ。
ハルはいない。
それでも、私はここにいる。
鳴かない朝の終わりに、
声に出さずに呼ぶ。
――ハル。
返事はない。
でも、名前はここに残った。
残った名前のそばで、
私は次の時間を迎える。
第2話へ続く・・・