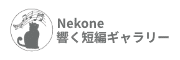【短編小説全10話】第七話:月明かりの下の変身、人ならざる姿
1.
私の部屋――いや、「元・私の部屋」には、鉄錆と、焦げたような異臭が立ち込めていた。 あの男たちが蹴りつけたドアの歪み。シズクが放った赤橙色の閃光が残した、空気の焼け焦げた匂い。
私は、震える手でキャリーバッグのファスナーを閉めた。 中には、ぐったりとして動かないシズク。体温は依然として高く、小さな身体が発する熱が、バッグ越しにも伝わってくる。
「……行かなきゃ」
ここに留まれば、彼らは必ず戻ってくる。次はもっと大勢で、もっと周到な準備をして。 私は、財布とスマホ、最低限の着替え、そしてシズクの残りのフードと水をリュックに詰め込んだ。 部屋を見渡す。 A子との友情を取り戻したパソコン。シズクが爪を研いだ柱の傷跡。二人で眠ったベッド。 この数ヶ月で築き上げた「温かい場所」のすべてが、今は遠い過去の遺跡のように見えた。
「……さようなら」
私は電気を消し、歪んだドアを無理やり押し開けて、夜の冷気の中へと飛び出した。
=================
2.
深夜の街は、敵意に満ちていた。 今まで、シズクの力で穏やかに見えていたこの街。商店街の活気も、人々の笑顔も、今はすべてが嘘のように感じられた。
路地裏の影が、あの男たちに見える。 風の音が、誰かの足音に聞こえる。 コンビニの白い光すら、私たちを暴き出すサーチライトのようで、まともに歩けなかった。
(どこへ行けばいい?)
ホテル? ダメだ。ペット不可のところが多いし、何より足がつくかもしれない。 A子の家? 巻き込むわけにはいかない。 ネットカフェ? シズクが鳴いたら終わりだ。
私は、キャリーバッグを抱きしめながら、人気の少ない河川敷へと向かった。 ここなら、少なくともビルの影から誰かが見ていることはない。
11月の夜風は冷たく、薄手のコートしか羽織ってこなかった私の体温を容赦なく奪っていく。 けれど、腕の中のキャリーバッグだけが、異様に熱かった。
「シズク、大丈夫? もう少しだからね……」
声をかけても、返事はない。 苦しそうな寝息だけが、私の耳元で繰り返されていた。
=================
3.
河川敷の、橋の下。 コンクリートの橋脚の陰に、私は身を隠した。 川の水音が、周囲の雑音を消してくれる。ここなら、少しは安全かもしれない。
私はリュックからタオルを取り出し、冷たい川の水で濡らして、キャリーから出したシズクの体を拭いた。
「熱い……」
熱は下がるどころか、さらに上がっているようだった。シズクの意識は混濁しており、琥珀色の瞳はうつろに開かれたまま、どこか遠くを見つめている。
「お願い、シズク。死なないで……」
涙が、シズクの頬に落ちた。 私のせいだ。私が、この子の力を過信して、街の噂を放置したから。 私が、もっと早く危険に気づいていれば。
(このままじゃ、朝を迎える前に……)
絶望が、夜の闇よりも濃く、私を包み込もうとしたその時だった。
ザッ、ザッ、ザッ……
土手を歩く、複数の足音。 そして、枯草を踏みしめる音が、こちらに近づいてくる。
「……この辺りじゃないか? さっきの光」
「川の方に逃げたって目撃情報があったぞ」
あの男たちの声だ。 仲間を連れて、戻ってきたのだ。
私は息をのんだ。シズクを抱きしめ、コンクリートの壁に背中を押し付ける。 心臓の音がうるさすぎて、見つかってしまうのではないかと思った。
足音が止まる。 橋の下を、懐中電灯の光が薙ぎ払った。
「……おい、そこ。誰かいるのか?」
見つかった。
=================
4.
「女と、猫だ! ここにいたぞ!」
男たちが、土手を駆け下りてくる。 三人、いや、四人か。 逃げ場はない。背後は冷たい川。前方は、欲望に目をぎらつかせた追手たち。
「橘さんよぉ。手間かけさせやがって」
リーダー格らしき男が、ニヤニヤと笑いながら近づいてくる。手には、動物捕獲用のネットのようなものを持っていた。
「その猫、渡せば悪いようにはしねえよ。億の価値があるんだ。分け前くらいくれてやる」
「……嫌っ!」 私は叫んだ。シズクをさらに強く抱きしめる。 「この子は、モノじゃない!」
「チッ。強情な女だ。おい、やれ」
男たちが、ジリジリと包囲網を狭めてくる。 私は、目を瞑った。
(ごめん、シズク。守れなかった……)
その時。
厚い雲が切れ、隠れていた満月が顔を出した。 冷たく、青白い月光が、橋の下の闇を切り裂き、私とシズクを照らし出した。
ドクン。
私の腕の中で、シズクの心臓が、ありえないほど強く脈打った。 え? と目を開けた瞬間。
シズクの身体が、燃え上がった。
いや、違う。 シズクの身体から、あの赤橙色の光が、爆発するように噴き出したのだ。 それは、アパートで見た時よりも遥かに強く、激しく、そして神々しい光だった。
「うわあっ!? なんだ、この光!?」
男たちが、たまらず後ずさる。
光は、渦を巻きながら、私の目の前で形を変えていく。 私の腕から離れた光の塊は、どんどん大きくなり、そして――
私の前に、「それ」は立っていた。
それは、猫ではなかった。 月光を背負い、揺らめく赤橙色の炎でできた、巨大な獣のシルエット。 大型犬よりも大きく、しなやかで、力強い四肢。 そして、その顔にあるのは、燃え盛る二つの巨大な、琥珀色の瞳。
『――グルルルルゥゥゥ……』
腹の底に響くような、低い唸り声。 それは、野生の獣の威嚇であり、同時に、何者をも寄せ付けない、守護神の警告だった。
「ひ、ひいぃっ!? バケモノだ!!」
「話が違うぞ! なんだあいつは!!」
男たちは、腰を抜かし、あるいは悲鳴を上げて、蜘蛛の子を散らすように逃げ出した。 ネットも、懐中電灯も放り出して。
=================
5.
河川敷に、静寂が戻った。 残されたのは、私と、目の前に立つ、光り輝く「人ならざる姿」。
私は、恐怖を感じなかった。 その巨大な光の獣は、私に背を向け、逃げていく男たちを睨みつけていたからだ。 その背中は、あまりにも頼もしく、そして、どこまでも優しかった。
「……シズク、なの?」
私が震える声で問いかけると、光の獣は、ゆっくりとこちらを振り向いた。 巨大な琥珀色の瞳が、私を見下ろす。 その瞳は、いつものシズクの、あのすべてを包み込むような穏やかな瞳そのものだった。
光の獣は、私に近づくと、その巨大な頭を、私の肩に擦り付けた。 ジュッ、と音がして、私のコートが少し焦げた。 けれど、不思議と熱くはなかった。
(ああ……やっぱり、シズクだ)
私を守るために。最後の力を振り絞って、こんな姿になってまで。
やがて、月が再び雲に隠れると同時に、光の獣の輪郭が崩れ始めた。 炎が小さくなり、元の小さな形へと収束していく。 最後に残ったのは、地面に横たわる、小さな茶トラの身体だった。
「シズク!」
私は駆け寄り、抱き上げた。 熱は、嘘のように引いていた。 穏やかな寝息。今度こそ、ただの深い眠りについているようだった。
私は、月を見上げた。 私たちは助かった。けれど、もう後戻りはできない。 シズクは、ただの「不思議な力を持つ猫」ではない。 もっと強大で、人知を超えた存在。
私は、この小さな、けれど偉大な守護者を抱きしめ、朝が来るのを待った。 ホームレスとなった最初の夜は、皮肉にも、今までで一番、確かな温もりに包まれていた。
第六話へつづく・・・