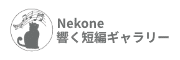【短編小説全10話】第九話:影の世界の歩き方、潜む気配
1.
夜の繁華街は、まばゆいネオンと騒音で溢れかえっていた。 行き交う人々は皆、それぞれの目的地に向かって歩いている。昨日までの私も、その中の一人だった。 けれど今は、透明な壁一枚隔てた向こう側の世界にいるような感覚だった。
リュックの重みが肩に食い込む。その中のキャリーバッグで、シズクがじっと息を潜めている気配を感じる。
「……まずは、今夜の寝床」
私は、フードを目深にかぶり、監視カメラの死角を探すように歩いた。 駅のコインロッカーに、かさばる荷物の一部を預けた。残りの現金を確認する。当面は持つだろうが、無駄遣いはできない。クレジットカードは足がつくから使えない。
街行く人の視線が怖い。すれ違う男たちが、全員あの襲撃者の仲間のように見えて心臓が縮む。 これが「追われる者」の感覚なのか。
私は、路地裏にある古びた雑居ビルの前に立った。「24時間営業・完全個室」と書かれたインターネットカフェの看板が、毒々しい光を放っている。 ここなら、身分証の提示も甘く、人の目も少ないかもしれない。
=================
2.
受付の気だるげな店員に現金を渡し、指定されたブースに入る。 狭く、タバコの臭いが染み付いた薄暗い空間。けれど、鍵がかかる扉があるだけで、少しだけ呼吸が楽になった。
リュックを床に置き、そっとキャリーバッグのファスナーを開ける。
「ごめんね、シズク。狭かったでしょ」
シズクは音もなく這い出すと、狭いリクライニングチェアの隅に身を丸めた。
「にゃあ」
小さく、短く鳴く。大丈夫だよ、と言っているかのようだった。
私はコンビニで買ったおにぎりと水を、シズクと分け合った。 質素な食事だが、喉を通ると少しだけ生きた心地がした。シズクは、私の膝の上で大人しくフードを食べている。
その小さな背中を撫でる。指先に伝わる体温は、今は穏やかだ。 けれど私は知っている。この小さな体の中に、あの巨大な炎の獣が眠っていることを。
「……私たち、本当にすごいことになっちゃったね」
シズクは食事を終えると、私の顔を見上げ、ザラザラした舌で頬をひと舐めした。 その瞳は、不安に押しつぶされそうな私の心を、静かに肯定していた。
=================
3.
シズクが眠りについたのを確認して、私はブースのパソコンに向かった。 履歴が残らないシークレットモードを使い、検索を始める。
昨夜の河川敷の騒ぎ。何かニュースになっていないか。 検索結果を見て、私は背筋が凍った。
『河川敷で不審火騒ぎ、けが人なし』
『近隣住民「何かが爆発したような光を見た」』
小さな地方ニュースの扱いで、数件の記事が出てきただけだった。 あの巨大な炎の獣のことも、逃げ惑う男たちのことも、一切触れられていない。ただの「不審火」や「いたずら」として処理されようとしていた。
(……もみ消されている?)
あの男たちは、ただのチンピラじゃなかった。 警察やメディアにすら圧力をかけられる、強大な組織の末端だったのだ。
アパートの襲撃も、きっと「個人的なトラブル」として処理されているのだろう。A子がニュースを見たと言っていたが、おそらく私が被害者ではなく、何かトラブルの原因を作った側のように報道されている可能性すらある。
「……孤立無援、か」
私は、社会から完全に切り離されたのだと悟った。 敵の姿は見えない。けれど、街全体が巨大な監視網のように思えてくる。
=================
4.
パソコンの画面を消すと、ブースの中は再び薄暗い闇に包まれた。 隣のブースから聞こえるいびきや、廊下を歩く足音が、神経を逆なでする。
私は椅子の上で膝を抱え、シズクを胸に抱き寄せた。 この温もりだけが、今の私に残された唯一の真実だ。
「……絶対に、渡さない」
私は暗闇の中で、誰にともなく呟いた。 あの炎の夜、シズクが私を守ってくれたように。今度は私が、この子を守り抜く番だ。
シズクの琥珀色の瞳が、暗闇の中で微かに発光したように見えた。 それは、底なしの闇の中の、唯一の灯台の光のようだった。
私たちは、狭いブースの中で身を寄せ合い、長く、浅い眠りについた。 明日から始まる、終わりの見えない逃亡生活への不安と、奇妙な高揚感を抱えながら。
最終話へ続く・・・