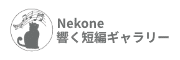【短編小説全10話】第五話:『猫の報恩』が囁く、街の噂
1.
季節は、秋へと移ろいでいた。 埼玉のこの街に引っ越してきてから、二ヶ月が経とうとしている。 私、橘 美咲(たちばな みさき)の生活は、驚くほど穏やかだった。
仕事は順調だ。コンペで勝ち取ったデザイン案件は、クライアントから高い評価を受け、さらに次のプロジェクトの打診も来ている。A子との関係も修復し、来月には久しぶりに二人で食事に行く約束もした。 経済的な余裕も、少しずつだが生まれ始めている。
だが、私の心には、ひとつだけ小さな「さざ波」が立っていた。 それは、シズクのことだ。
「……シズク、また昨日も、出かけてたの?」
日曜日の朝。 ベランダの窓際で、シズクが熱心に毛づくろいをしている。その足元には、どこから拾ってきたのか、色づいた銀杏(いちょう)の葉が一枚、落ちていた。 ここ数週間、シズクは夜中に姿を消すことが増えた。 第2話の時のように、チリリ……という不思議な音と共にいなくなり、夜明け前には必ず戻っている。
最初は心配で眠れなかったが、シズクは必ず私の枕元に戻ってくるし、怪我をしている様子もない。 ただ、戻ってきた時のシズクは、どこか「一仕事終えた」ような、満足げな顔をしているのだ。
「あんた、この街で何をしてるの?」
私はシズクを抱き上げる。 シズクは「ニャ(秘密)」とでも言うように、私の鼻先に自分の鼻を押し付けた。 その琥珀色の瞳は、相変わらず深く、そして以前よりも増して、神秘的な光を湛えていた。
=================
2.
その日、私はシズク用の新しい爪とぎを買いに、駅前の商店街へと出かけた。 この街の商店街は『夕凪(ゆうなぎ)通り』と呼ばれ、昭和の面影を残すレトロな雰囲気が気に入っていた。 しかし、シャッターを下ろしたままの店も多く、活気があるとは言い難い。
「あら、こんにちは」
声をかけられ、振り返る。 そこには、商店街の入口にある小さな和菓子屋『小春堂』の女将さん、トヨさんが立っていた。
「あ、こんにちは。トヨさん」
引っ越してきてすぐに、挨拶がてら大福を買って以来、顔見知りになっていた。 トヨさんは、いつもならニコニコしているのに、今日はどこか浮かない顔をして、店先の掃除をしていた。
「元気ないですね、どうしたんですか?」
「ああ、いやね……。ここ最近、お店を閉めようかと思っててね」
「えっ、閉めるんですか? 大福、美味しいのに」
「主人が亡くなってから一人でやってきたけど、最近はめっきりお客さんも減ってねぇ。それに……」
トヨさんは言葉を濁した。
「……大事なものを、失くしちゃってね。それが、潮時かなって」
大事なもの。 詳しく聞こうとしたその時、私のトートバッグの中から、顔を出していたシズクが、身を乗り出した。 「ミャ!」 鋭く、短い鳴き声。
シズクは、バッグから飛び降りると、トヨさんの足元に擦り寄った。
「あらあら、可愛い猫ちゃんねぇ。連れてきたの?」
トヨさんの顔が少しほころぶ。 シズクは、トヨさんのエプロンの匂いを嗅いだ後、くるりと反転し、店の奥――普段は客が入らない、住居スペースの方へ向かって歩き出した。
「あ、こら、シズク! ダメだよ!」
私が慌てて追いかけようとすると、シズクは立ち止まり、琥珀色の瞳で私とトヨさんを振り返った。 チリリ…… 昼間だというのに、あの音が聞こえた気がした。
「……ついておいで、って言ってるのかい?」
トヨさんが不思議そうに呟き、シズクの後を追った。
シズクが向かったのは、店の裏庭にある、古い物置の前だった。 物置の屋根の隙間。 シズクはそこをじっと見上げ、「ニャア」と鳴いた。
トヨさんが、踏み台を持ってきて、その隙間を覗き込む。
「……あっ!」
トヨさんの震える手が、そこから何かを取り出した。 それは、古びた小さな巾着袋だった。
「……これ、旦那の形見の……印鑑と、通帳が入った袋……!」
トヨさんは、巾着袋を胸に抱きしめ、その場に崩れ落ちた。
「どうして……泥棒に入られたと思って、もう諦めてたのに……。カラスか何かが、隠したのかしら……」
トヨさんは涙を流しながら、シズクの頭を何度も撫でた。
「ありがとう、ありがとうねぇ。猫の神様みたいだねぇ」
シズクは、当然のことをしたまでです、といった顔で、尻尾をゆらりと揺らした。
その時、私は見た。 シズクの身体から、ごく薄い、金色の粒子が舞い上がり、それが『小春堂』の店全体を包み込んでいくのを。
=================
3.
異変が起きたのは、その翌週からだった。
会社帰りに商店街を通ると、妙な光景を目にした。 いつも閑散としていた『小春堂』の前に、行列ができているのだ。
「えっ……?」 驚いて見ていると、行列の客たちが話している声が聞こえてきた。
「ここの大福、食べると運気が上がるらしいよ」
「なんでも、不思議な猫が福を運んできたって噂でさ」
「『琥珀色の猫』を見ると、失くし物が見つかるんだって」
私の背筋に、冷たいものが走った。 琥珀色の猫。 間違いなく、シズクのことだ。
トヨさんが店から出てきて、忙しそうに、でも最高に嬉しそうな笑顔で客を捌いている。 私に気づくと、トヨさんは駆け寄ってきた。
「橘さん! 見てちょうだい、これ! あの日から、急にお客さんが増えて……。SNSとかいうので、誰かが広めてくれたみたいでね。『幸運の招き猫がいる店』だって!」
トヨさんは声を弾ませる。
「あの子、シズクちゃんって言ったわよね? あの子は、本当に福の神だよ。店を閉めるなんて、バカなこと考えなくてよかった!」
私は、引きつった笑顔で「よかったですね」と返すのが精一杯だった。
=================
4.
噂は、『小春堂』だけでは止まらなかった。
「駅前の公園で泣いていた迷子を、茶色い猫が家まで案内した」
「就職活動に失敗続きだった大学生が、夜中に光る猫とすれ違ったら、翌日に内定が出た」
「夫婦喧嘩で家を出た夫が、猫の鳴き声に導かれて、思い出の場所で妻と再会した」
街のあちこちで、「琥珀色の瞳を持つ猫」の噂が囁かれ始めていた。 人々はそれを、親しみを込めて、あるいは畏敬の念を持ってこう呼んだ。
『夕凪通りの、報恩猫(ほうおんねこ)』
夜、私はシズクを問い詰めた。
「ねえ、シズク。あんた、やりすぎだよ」
私の膝の上で、シズクは無邪気に自分の尻尾を追いかけて遊んでいる。
「みんなが幸せになるのは、いいことだよ。でも……」
私は怖いのだ。 シズクの力が、公になりすぎることが。 トヨさんのように純粋に感謝してくれる人ばかりならいい。 けれど、「幸運」は、時に人の「欲望」を刺激する。
「もし、悪い人が、あんたの力を利用しようとしたら……」
私が抱く不安をよそに、街の空気は熱を帯びていった。 商店街は活気を取り戻し、あちこちで笑顔が増えた。それは間違いなく、シズクが夜な夜な撒いた「金色の種」が芽吹いた結果だった。
私の孤独を救った「恩返し」は、いつしか枠を超え、この街全体の「冷たさ」や「寂しさ」を修復する、大きなうねりとなっていたのだ。
=================
5.
ある晩のこと。 私は、コンビニからの帰り道、路地裏で二人の男が話しているのを耳にした。
男たちは、スーツ姿だが、どこか柄が悪かった。 手には、何かの探知機のようなものを持っている。
「……ここら辺で、反応があったんだよな」
「ああ。『例の猫』だろ? 都市伝説かと思ったが、どうやらマジらしいぞ」
「捕まえれば、億単位の価値があるって話だ」
「飼い主は? 分かってんのか?」
「ああ、だいたい目星はついてる。この近くのアパートに住む、若い女だ」
心臓が、早鐘を打った。 買い物袋を握りしめる手が、ガタガタと震える。
(見られてる……?)
私は息を殺し、その場を離れた。 アパートまでの道のりが、永遠に感じられた。 背後に、誰かの視線を感じる。 冷たく、粘着質な、欲望の視線。
部屋に飛び込み、鍵をかけ、チェーンをかける。
「……はぁっ、はぁっ……」
シズクが、玄関まで迎えに来てくれた。
「ニャアン?」
いつも通りの、のんきな声。 だが、私はシズクを抱きしめ、震えが止まらなかった。
「シズク……見つかっちゃったかもしれない」
街に広がる「幸せな噂」の裏側で、黒い影が確実に忍び寄っていた。 シズクの恩返しが大きくなればなるほど、その光は強く、そして影もまた、濃くなっていく。
窓の外。 雨も降っていないのに、遠くで雷鳴のような音が響いた。 私の平穏な日常は、終わりを告げようとしていた。
=================
6.
翌日。 私の部屋のポストに、一通の手紙が入っていた。 差出人の名前はない。 中には、一枚の写真と、短いメッセージが入っていた。
写真は、夜中の公園で、金色の光を放つシズクを捉えたものだった。 そして、メッセージには、こう書かれていた。
『あなたの猫の奇跡を、独り占めするのは良くないですね。近々、お話を伺いに参ります』
私は、その手紙を握りつぶした。 シズクを見る。 シズクは、窓の外をじっと見つめている。 その瞳は、琥珀色から、深く、鋭い金色へと変わりつつあった。
それは、来るべき敵を迎え撃つ、戦士の瞳だった。
「……守るよ」
私は呟いた。
「今度は、私が守る番だ」
街が囁く『猫の報恩』。 その優しい噂は、今、私たちにとって最大の「試練」の呼び水となってしまった。
第六話へ続く・・・