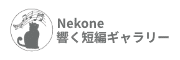【短編小説全10話】第一話:雨の日の出会いと、小さな命の選択
1.
アスファルトを叩く無慈悲なピアノ。それが、私、橘 美咲(たちばな みさき)、26歳の日常を締めくくるBGMだった。
ザー、ザー、ザー。 正確なリズムでフロントガラスを打つ雨粒は、ワイパーによって無造えに引き裂かれ、またすぐに新しい粒がその場所を埋めていく。カーステレオから流れる流行りの曲は、とっくに雨音にかき消されていた。
(また、今日も、終わった)
会社と家の往復。片道1時間半の満員電車。今は、会社の最寄り駅から自分のアパートの最寄り駅まで、金曜日の夜だというのに、虚無を乗せて走る最終バスの中だ。 窓の外を流れるネオンが、雨粒に屈折して、まるで泣いているように滲んでいる。涙色の風景。
今週も、何をしたわけじゃない。 正確には、「何かをした」という実感がない、と言うべきか。 朝9時に出社し、無機質なグレーのデスクでパソコンを開く。上司に言われた資料を修正し、定型文のメールを何十通もさばき、鳴り響く電話に「申し訳ございません」と頭を下げる。気づけば時計の針は18時を回り、そこからさらに「キリがいいところまで」と残業し、今に至る。
「使い捨ての今日が、また終わる」
誰にも聞こえない声で、心の中だけで呟く。 疲れていた。身体も、だけど、それ以上に心が。 誰かに必要とされている実感も、明日が今日より良くなるという確信もない。ただ、生きるために働き、働くために生きる。その螺旋階段を、目隠しされたまま下り続けているような感覚。
バスが、ガコン、と大きな音を立てて停車した。 「終点、桜木町駅前。お降りの方は……」 無機質なアナウンスが、私を現実(アパート)へと引き戻す。重い身体を引きずり、湿った空気の充満するバスを降りた。
バサッ。 折り畳み傘を開く音が、やけに大きく響く。 冷たい。 傘を突き抜けてくるような、六月の冷たい雨。ジャケットの襟を立て、うつむき加減に歩き出す。ここからアパートまでは、徒歩12分。私にとっては、一日で最も孤独を感じる時間だ。
商店街はとうにシャッターを下ろし、煌々と光っているのはコンビニの明かりだけ。その白い光が、雨に濡れた路面を不気味に照らし出している。 私はその光を避けるように、裏路地を選んで歩いた。近道だから、というのもあるけれど、あの明るすぎる光が、今の自分の薄汚れた疲労感を際立たせるようで、嫌だった。
静かな住宅街。響くのは、自分のヒールが水たまりを避ける音と、傘を叩く雨音だけ。 ……そのはずだった。
「…………ミャ、…」
不意に、ノイズが混じった。 空耳だろうか。 あまりに弱々しく、雨音の隙間に割り込んでくる、細い音。 立ち止まる。 心臓が、ドクン、と小さく跳ねた。
「……ミャア、……ミィ……」
聞こえる。 間違いない。 雨音の重低音の隙間を縫って、必死に絞り出すような、甲高い、けれど消え入りそうな声。
私は、音のする方へ、まるで見えない糸に引かれるように足を向けた。 アパートの駐輪場の、その影。ゴミ捨て場のすぐ隣。 そこに、それはあった。
=================
2.
びしょ濡れの段ボール。 「ご自由にお持ちください」と書かれたマジックの文字が、雨に滲んで泣いているように見える。だが、中身はフリーペーパーや古着ではなかった。
段ボールは、すでにその役目を放棄しかけていた。ふやけて形を失いかけた箱の隅で、小さな何かが、かろうじて動いていた。
「…………っ」
息をのんだ。 手のひらに乗るくらいの、小さな、黒い塊。 それが、子猫だと認識するのに、数秒かかった。
全身がずぶ濡れで、本来の色も分からない。寒さと恐怖で、その小さな身体を必死に震わせている。 そして、私という大きな存在に気づくと、最後の力を振り絞るように、口を小さく開けて、声にならない声を上げた。
「ミィ……」
その声は、私の心のいちばん柔らかい場所を、鋭く抉った。 雨の冷たさとは違う種類の冷たいものが、背筋を走る。
(ダメだ)
即座に理性が警鐘を鳴らす。 私のアパートは、『第二さくら荘』。木造二階建て、オートロックもエレベーターもない、築30年の古いアパート。そして、契約書にはっきりと、太字でこう書かれていた。
【ペット飼育、一切不可】
見つかれば、即刻退去。あるいは、高額な違約金。 ただでさえ、毎月の手取りから家賃と奨学金の返済を引けば、残るのは雀の涙。そんなリスク、到底負えない。
(……見なかったことにしよう)
それが、大人の、正しい選択だ。 私はこの26年間、そうやって「正しい選択」を積み重ねてきた。波風を立てず、ルールを守り、誰にも迷惑をかけず、ひっそりと息をすること。
私は踵を返そうとした。 自分の部屋の、温かい(といってもエアコンが効くまで30分はかかるが)布団のことだけを考えようとした。
「…………ミャ、」
雨音が、一瞬、遠のいた。 その隙間に、諦めたような、小さな小さな鳴き声が、私の足首に絡みついた。
動けなかった。
(このまま、私が立ち去ったら) (この子は、どうなる?)
考えるまでもない。 気温は下がり続けている。この雨だ。朝を迎える前に、この小さな命の火は、静かに消えるだろう。 誰にも知られず、この冷たい段ボールの中で。
それは、まるで、今の私自身を見ているようだった。 都会の片隅で、誰にも必要とされず、ただ無意味に消耗していく自分。もし私がここで動けなくなったら、誰かが気づいてくれるだろうか。
(……五分) 脳内で、誰かがそう言った。 (五分だけ。温めて、何か食べさせて……それから、考えよう)
私は、何を考えているのだろう。 「ひとまず」が、どれだけ危険な言葉か知っているはずなのに。 それでも、私の身体は、理性の命令を無視して動いていた。
バッグから、会社で使っているタオルハンカチを取り出す。それで子猫を包もうとして、あまりのずぶ濡れ具合にためらった。 「……ごめん、ちょっと待ってて」 誰に言うともなく呟き、ジャケットを脱いだ。上質なカシミア、なんてものじゃない。二年前に買った、安物の化繊のジャケット。けれど、今の私が出せる、最大限の温もりだった。
ジャケットの内側の、まだ乾いている部分で、子猫の身体を乱暴にならないように、けれど必死に拭う。冷え切った身体は、氷のようだった。 「……ミャ……」 抵抗する元気もないのか、弱々しく鳴いた。
私は子猫をジャケットごと抱え上げ、傘も差さず、自分のアパートに向かって走り出していた。 ヒールが水たまりを蹴散らし、泥水がスカートに跳ね上がるのも構わなかった。
=================
3.
『第二さくら荘』の102号室。 それが私の「城」であり、「檻」だった。
鍵を開ける手が、焦りで震える。子猫を抱いているため、片手での作業がもどかしい。 カチャリ、と安っぽい音がして、ドアが開く。 私は転がり込むように室内に入り、即座に鍵を閉め、チェーンまでかけた。
「……はぁっ、はぁっ……」
荒い息が、静かなワンルームに響く。 電気もつけず、玄関のたたきに座り込んだ。腕の中の温もり(いや、まだ冷たい)が、かろうじて動いていることを確認する。
(……やっちゃった)
ルール違反の温もり。 背徳感が、じわりと胸に広がる。 隣の101号室は、大家さんが住んでいる。壁は、驚くほど薄い。 もし、鳴かれたら? 一発でバレる。
「……お願いだから、静かにしてて」 私は、腕の中の小さな命に囁きかけた。
まずは、温めないと。 私は慌てて立ち上がり、リビング(と呼べるほど広くもないが)の電気をつけた。 エアコンの暖房スイッチを、設定温度30度で入れる。ゴオオ、と古い機械が唸りを上げた。
バスタオルを数枚持ってきて、子猫の身体をもう一度、今度は丁寧に拭く。 黒だと思っていた毛色は、濡れたせいでそう見えただけだった。 乾いてくると、ところどころに茶色い差し色が入った、美しい茶トラ柄だと分かった。
そして、その瞳。 身体はあんなに汚れていたのに、その瞳だけは、まるで磨かれた宝石のようだった。 光の加減で金色にも緑色にも見える、不思議な色。 いや、違う。 これは――琥珀色だ。
「…………」
子猫は、私をじっと見つめていた。 怯えでもなく、威嚇でもなく、ただ、まっすぐに。 その琥珀色の瞳に射抜かれて、私は一瞬、言葉を失った。まるで、私の心の奥底まで、すべて見透かされているような、不思議な感覚。
「……お腹、空いてるよね」 私は慌てて視線をそらし、キッチンに向かった。 猫が何を食べるかなんて、考えたこともなかった。牛乳? いや、確かダメだって聞いたことがある。 スマホを取り出し、震える指で「子猫 拾った 応急処置」と検索する。 「人肌に温めた砂糖水か、猫用のミルク」
……猫用ミルクなんて、あるわけがない。 時計を見る。23時30分。近所のスーパーは閉まっている。開いているのは、ドン・キホーテか、少し離れた24時間営業のドラッグストア。
「待ってて。すぐ戻るから」 私は子猫をバスタオルでくるみ、ひとまず空の段ボール(アマゾンで届いたものだ)に入れて、その上からもタオルをかけた。 そして、財布と鍵だけを掴むと、再びアパートを飛び出した。 さっきまであれほど億劫だった身体が、嘘のように軽かった。
雨は、まだ降り続いていた。
=================
4.
ドン・キホーテのペットコーナーは、真夜中だというのに眩しいほどの照明で満たされていた。 猫用ミルク、哺乳瓶、ウェットフード、カイロ、ペット用ベッド……。 (こんなに、色々必要なんだ)
私は、言われるがままにカゴに入れていく。 子猫用のミルク。哺乳瓶のセット。それから、万が一のために、一番柔らかそうな「離乳用」と書かれたウェットフード。身体を温めるための、貼らないタイプのカイロ。 ふと、猫砂と小さなトイレが目に入った。 (……ダメだ、ダメだ。私は「ひとまず」保護しただけ) 「ひとまず」のはずなのに、私は無意識に、その先を考えようとしていた。
結局、猫砂とトイレは棚に戻し、最低限のものを買って店を出た。 レシートに印字された「5,480円」という数字が、やけに重く感じた。今月の食費が、また厳しくなる。
アパートに戻ると、段ボールの中の子猫は、不安そうに身をすくめていた。 「ただいま。怖かったよね、ごめん」 私は説明書を読みながら、慣れない手つきでミルクを作った。人肌より少し熱いくらい。 哺乳瓶の先を口元に持っていくと、子猫は最初、それが何だか分からないようだったが、ミルクの匂いを嗅ぐと、小さな口で必死に吸いつき始めた。
「……チュ、チュ……」
小さな、小さな音が、部屋に響く。 それが、私を縛り付けていた無機質な雨音を、少しずつ溶かしていくようだった。
「……美味しい?」 子猫は、琥珀色の瞳を細め、夢中でミルクを飲んでいる。 ゴクン、と喉を鳴らすたびに、細い尻尾がぴくりと揺れる。
(……生きてる)
当たり前のことなのに、その実感が、雷に打たれたように私を貫いた。 この子は、生きようとしている。 こんなに冷たい世界で、たった一人で、必死に声を上げて、生きようとしていたんだ。
ミルクを飲み終えると、子猫は安心したのか、私の手のひらの中で、ふ、と身体の力を抜いた。 「……フゥ…」 満足げな、小さな寝息。 私は、その温かさに、泣きそうになった。
=================
5.
それから、数日が過ぎた。 土曜と日曜は、幸い休みだった。私はほとんどの時間を、子猫の世話に充てた。 「隠す」というのは、想像以上に神経を使う作業だった。
子猫は、私が「シズク」と仮の名前を付けた。雨の雫から取った、単純な名前だ。 シズクは、驚くほど静かな猫だった。 私が部屋にいる時は、鳴かない。私がトイレや風呂に行こうとすると、不安そうに「ミャ」と短く鳴くが、それも大家さんに聞こえるほどの声量ではない。 まるで、自分の置かれた状況を理解しているかのように。
問題は、月曜日。 会社に行かなければならない。 シズクを、このペット禁止のアパートに、一匹で残して。
(どうしよう)
土曜の夜、私は通帳と睨めっこしていた。 シズクを保護してから、動物病院にも連れて行った。幸い、猫風邪を少し引いている程度で、ノミやダニも駆除してもらい、健康状態は悪くないとのことだった。 だが、診察代と薬代で、1万5千円が飛んだ。 ドン・キホーテでの買い物と合わせ、この数日で2万円以上の、予定外の出費。
貯金残高は、284,500円。 これが、私の全財産だった。
26歳、社会人4年目。あまりに情けない金額だ。 奨学金の返済がなければ、もう少しマシだったかもしれない。けれど、それが現実だった。
(このお金じゃあ……)
引っ越しなんて、不可能だ。 敷金、礼金、仲介手数料、前家賃。都内でペット可の物件となれば、それだけでこの貯金は一瞬で消え去る。 そもそも、ペット可の物件は、今の家賃よりも確実に高くなる。
(……無理だ)
理性が囁く。 (このまま隠して飼うか? でも、必ずバレる。その時のリスクは?) (それとも……)
最悪の選択肢が、頭をよぎる。 「里親」を探す。 それが、シズクにとっても、私にとっても、一番「現実的」な解決策かもしれない。 スマホで「猫 里親 東京」と検索する。 たくさんのサイトがヒットした。
「……ごめんね、シズク」 私は、毛布の上で丸くなって眠るシズクの、小さな頭を撫でた。 「私じゃ、ダメみたいだ……」
その時だった。 シズクが、ゆっくりと目を開けた。 あの、琥珀色の瞳。 夜の部屋で、それはランプのように、静かに、強く光っていた。
シズクは、私の指先に、自分の小さな頭をこすりつけてきた。 ゴロゴロ…… 喉の奥で、小さなエンジンがかかったような音がする。
それは、私への、絶対的な信頼の音だった。
(……ああ)
私は、何てバカなんだろう。 お金がないから? ルール違反だから? リスクがあるから?
だから、何だというのだ。
私は、この数日間、忘れていた感覚を思い出していた。 「誰かのために」必死になること。 この子の命を守るために、雨の中を走ったこと。 この子の寝息を聞くために、神経をすり減らしたこと。
それは、疲労困憊だった私の日常の中で、唯一、「生きている」と実感できた瞬間だった。
(この温もりを、手放せるのか?) (また、あの無機質な、雨音だけの世界に戻るのか?)
答えは、出ていた。
=================
6.
私は、スマホの検索窓に、違う言葉を打ち込んだ。
「ペット可 賃貸 格安 東京」
無謀だ。 分かっている。 貯金はゼロになるだろう。 引っ越した先での生活は、今よりもっと厳しくなる。
それでも、私は検索を止めなかった。 シズクが、私の膝の上によじ登ってきた。 小さな爪が、少しだけ食い込む。痛い。けれど、それが嬉しい。
「……シズク」 私は、決意を込めて、その小さな名(仮)を呼んだ。 「……私たち、引っ越そう」
シズクは、私の言葉が分かったかのように、「ニャア」と短く、力強く鳴いた。 それは、あの雨の日とは比べ物にならないほど、生命力に満ちた声だった。
私は、通帳を閉じた。 284,500円。 これが、私のゼロからのスタートラインだ。 このお金は、もう私一人のものではない。私と、この小さな命が、新しい場所で生きるための、最初の軍資金だ。
(大丈夫。何とかなる)
いや、何とかするんだ。 会社と家の往復だった、灰色の世界。 その世界に、琥珀色の光が差し込んだ。
もう、雨音は怖くない。 これからは、この子の喉を鳴らす音、ささやかな足音が、私のBGMになるのだから。
私は、シズクを強く抱きしめた。 この小さな命を最優先にすると決めた、この選択を。 これが、後に私の人生を根底から変える「恩返し」の序章になるとは、この時の私は、まだ知る由もなかった。
第二話へ続く・・・