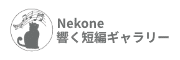【短編小説全10話】第六話:試練の足音、迫る冷たい視線
1.
街の空気が、変わった。
それを肌で感じたのは、あの脅迫めいた手紙が届いてから数日後のことだった。 会社帰りに立ち寄った『夕凪通り商店街』。
かつては閑古鳥が鳴き、少し前までは「報恩猫」の噂で温かい活気に満ちていたその場所は、今、異様な熱気に包まれていた。
「ねえ、まだ出ないの? 例の猫」
「ここで待ってれば会えるって聞いたんだけど」
「宝くじ買ったから、撫でさせてほしいんだよね」
そこかしこから聞こえてくるのは、感謝ではなく、焦りと欲望の声だった。 人々は血走った目でキョロキョロと辺りを見回し、野良猫が通るたびに「あれか!?」と殺到する。
トヨさんの和菓子屋『小春堂』の前は、もっと酷かった。
「ちょっとお婆さん、猫はいつ来るんだよ!」
「ここの大福食ったけど、全然いいことないじゃないか! 金返せ!」
行列は、クレームの嵐に変わっていた。トヨさんは困り果てた顔で、何度も頭を下げている。
「申し訳ありません、あの子は気まぐれで……」
私は、いたたまれなくなってその場を離れた。 (……私のせいだ)
シズクが撒いた「善意の種」は、人々の心の中で、いつしか「強欲の茨」に変わってしまっていた。 「もっと欲しい」「自分だけが得をしたい」。 そんな冷たく、粘着質な欲望が、街の空気をドブ川のように澱ませていた。
そして、その澱んだ空気は、確実にシズクを蝕んでいた。
=================
2.
「シズク……」
アパートの部屋。電気をつけても、どこか薄暗く感じる。 シズクは、私が帰宅しても玄関まで迎えに来なかった。 部屋の隅、一番暗い場所にあるベッドの下に潜り込み、丸くなっている。
引っ張り出してみると、シズクの体は熱かった。
「熱がある……」 あの、宝石のように輝いていた琥珀色の瞳は、今は光を失い、濁ったガラス玉のようになっていた。 喉のゴロゴロいう音も聞こえない。代わりに、苦しそうな、浅い呼吸が繰り返されている。
(どうしよう……!)
病院へ連れて行くべきか? だが、これは普通の病気なのだろうか? この街に充満する「負の感情」が、シズクの不思議な力を、生命力ごと削り取っているのではないか。
私は、熱いタオルでシズクの体を拭き、スポイトで水を飲ませた。 シズクは、ぐったりと私の腕に身を任せている。
「ごめんね。私が、もっと早く気づいていれば……」
あの、絹糸のような温もりは、今はどこにもない。 代わりに感じるのは、私の心臓を鷲掴みにする、氷のような恐怖だった。
その時だった。 ピンポーン。 突然のインターホンに、私は飛び上がった。
時計を見る。夜の10時過ぎ。 こんな時間に、誰が? 宅配の予定はない。A子でもない。
私は息を殺し、ドアの覗き穴(ドアスコープ)に目を当てた。
=================
3.
心臓が、止まるかと思った。
魚眼レンズで歪んだ視界の向こうに立っていたのは、以前、路地裏で見かけた、あの柄の悪いスーツの男たち二人組だった。
(……どうして、ここが)
あの手紙の主か。 彼らは、執拗にインターホンを鳴らし続けている。
「橘さーん。いるんでしょー? ちょっとお話があるんですけどねえ」
「あの『猫』のことでさあ。いい話持ってきたんだよ」
ドア一枚隔てた向こう側から聞こえる、粘着質な声。 私は、震える手で鍵がかかっていることを確認し、チェーンを握りしめた。 絶対に、開けてはいけない。
「……チッ。居留守かよ」
舌打ちが聞こえた。
「おい、例のやつ、試してみろ」
ガサゴソと音がして、何かの機械音が響いた。 キィィィィン…… モスキート音のような、耳障りな高周波音。
その瞬間、私の腕の中で、ぐったりしていたシズクが、ビクン!と跳ねた。
「フシャァァァッ!!」
シズクは、苦しそうに、しかし激しい威嚇の声を上げた。
「おっ、やっぱりいるな。反応があった」
「へへっ。やっぱり普通の猫じゃねえな。この特殊音波を嫌がるってことは」
彼らは、シズクの「力」を知っている。 そして、それを弱らせる方法も。
「橘さんよぉ。その猫、あんたには荷が重いんじゃないの?」
ドォン! 男の一人が、ドアを蹴飛ばした。古いアパートのドアが、悲鳴を上げて揺れる。
「……っ!」
私は悲鳴を噛み殺し、シズクを抱きしめて部屋の奥へと後ずさった。 ここは、二階。窓から逃げることはできない。 完全に、袋の鼠だった。
=================
4.
ドォン! ドォン! ドアを蹴る音は、どんどん激しさを増していく。鍵が壊れるのも、時間の問題かもしれない。
(どうする? 警察を呼ぶ?)
(でも、なんて説明する? 「光る猫を狙う男たちが来ました」なんて言って、信じてもらえる?)
思考がパニックに陥る中、腕の中のシズクが、もぞりと動いた。 シズクは、私の腕から抜け出し、よろよろと床に降りた。
「シズク、ダメ! 隠れてて!」
私が止めようとするのをすり抜け、シズクは、蹴り飛ばされて振動する玄関ドアの前に、立ちはだかった。
その姿は、あまりにも小さく、頼りなかった。 熱でふらついている。立っているのがやっとのはずだ。
けれど。 シズクは、ゆっくりと顔を上げ、ドアの向こうの気配を睨みつけた。
その瞬間。 濁っていたはずのシズクの瞳が、カッと見開かれた。
チリリリリリリリッ!!
いつもの鈴のような音ではない。 空気が裂けるような、鋭い警告音。 そして、シズクの全身から、光が迸(ほとばし)った。
それは、今までの温かい金色の光ではなかった。 攻撃的な、燃えるような 赤橙色(あかだいだいいろ) の閃光。
「――ギャアアアアッ!?」
ドアの向こうで、男たちの悲鳴が上がった。 まるで、見えない高圧電流に触れたかのように、何かが弾け飛ぶ音と、男たちが階段を転げ落ちていく音が響いた。
ドサドサッ、という音が遠ざかり、後には静寂が戻った。
=================
5.
私は、呆然と立ち尽くしていた。 今、何が起きたのか。
シズクが、力を、使ったのだ。 「癒やす」ためではなく、「拒絶する」ために。
「……シズク」
私が声をかけると、シズクはその場に崩れ落ちた。 赤橙色の光は消え、再び、苦しそうな呼吸に戻っている。
私は駆け寄り、シズクを抱き上げた。 体は、さっきよりもさらに熱くなっていた。まるで、最後の生命力を燃やし尽くしてしまったかのように。
「……ごめんね、シズク。ごめんね……」
私は泣きながら、シズクの体を冷やし続けた。 男たちは撃退できたかもしれない。けれど、これで彼らは確信したはずだ。 シズクが「本物」であることを。
もう、ここにはいられない。 あの視線は、執念深く私たちを追いかけてくるだろう。
私は、部屋を見渡した。 ようやく手に入れた、私とシズクの城。 トラウマを乗り越え、友情を取り戻した、大切な場所。
けれど、それらすべてを捨ててでも、守らなければならないものが、私の腕の中にあった。
窓の外、夜空には、不気味なほど赤い月が浮かんでいた。 試練の足音は、もう、ドアの前まで来ていたのだ。
私は、部屋の隅に置いてあった、引っ越しの時に使ったキャリーバッグを引っ張り出した。
第七話へつづく・・・