【短編小説全10話】第三話:琥珀色の瞳が見つめる、過去の影
1.
「――本当に、通った……」
スマートフォンの画面に表示された「審査通過」の四文字を、私は何度見直したか分からない。 あれから三日。 シズクの不思議な力に導かれるように電話した不動産屋で、私は半ばパニックになりながら内見を即決し、その場で申し込み用紙を書き殴った。
『第二さくら荘』の大家さんの目を盗んでシズクをキャリーバッグに隠し、会社用のカバンでカモフラージュして連れて行った、冷や汗だらけの内見。 「あ、あの、猫なんですけど、まだ小さくて……」 しどろもどろになる私に、不動産屋の担当者は、なぜか拍子抜けするほどあっさりと「あ、大丈夫ですよ。ここの大家さん、猫好きなんで」と笑った。
何もかもが、出来すぎている。 まるで、見えない誰かが私のために道を作ってくれているかのように、物事はスムーズに進んだ。
だが、代償は大きい。 審査通過の連絡と同時に送られてきた、初期費用の請求書。 家賃(前家賃)、仲介手数料、保証料、火災保険料……。 合計、214,000円。
私の全財産、284,500円。 それを支払えば、残りは、70,500円。
「……七万」
新居での生活費。光熱費の開通。引っ越し代。 そして、シズクのご飯と病院代。 指先が、冷たくなっていくのが分かった。
(でも、もう、戻れない)
私は、震える指で「振込実行」のボタンを押した。 スマホの画面が切り替わり、私の貯金残高が、あっけなく七万円台になった。 「これで、本当にゼロからだ」
足元で、シズクが「ミャ?」と私の顔を見上げていた。 その琥珀色の瞳は、私の不安を見透かすでもなく、ただ、ここにいるよ、と告げるように穏やかだった。
「……大丈夫。大丈夫よ、シズク」 私はシズクを抱き上げた。 「私たち、新しい家に行くんだから」
=================
2.
引っ越しは、地獄だった。 「業者に頼む」という選択肢は、最初からなかった。 私は会社を有給で三日間取り、まず、レンタカー屋で一番安い軽トラックを借りた。24時間で6,000円。
荷造りは、毎晩、シズクが寝静まった後、音を立てないように行った。 『第二さくら荘』の薄い壁は、段ボールにガムテープを貼る音すら、隣の大家さんの部屋に響きそうで恐ろしかった。
「シズク、お願いだから、今だけ静かにしてて」 シズクは、私がこそこそと動き回るのを、不思議そうに目で追っていた。 私が不安になると、シズクは必ず喉を「ゴロゴロ」と鳴らした。それは「大丈夫だよ」という、小さなお守りの音のようだった。
引っ越し当日。 私はシズクをキャリーバッグに入れ、その上からバスタオルをかけた。
「ちょっとだけ我慢してね」
心臓が、早鐘のように鳴っている。 大家さんに見つかれば、すべてが終わる。敷金どころか、違約金を請求され、残りの七万円すら失うかもしれない。
早朝5時。 私は息を殺し、まずシズクの入ったキャリーを軽トラックの助手席に運び込んだ。 そこから、自分の荷物の運び出し。 ベッド。 冷蔵庫(小さいもので助かった)。 服がパンパンに詰まった衣装ケース。 ローデスク。 本棚。
26歳、女性、一人。 その作業は、私の体力と精神力を容赦なく削り取った。
「……っ、う……!」
冷蔵庫を玄関から引きずり出す際、角を壁にぶつけてしまった。ガン、という鈍い音。 しまった、と息をのむ。
その瞬間、101号室のドアが、ガチャリ、と開いた。 「……!」 血の気が引いた。 現れたのは、寝間着姿の、険しい顔をした大家さんだった。
「……あんた、こんな早朝から、何をごそごそやってるんだい」
「あ……おはよう、ございます。あの、今日、引っ越しで……」
「引っ越し!? 昨日の夜まで、そんな話聞いてないよ!」
「も、申し訳ありません、急に決まって……」
大家さんの視線が、私の足元から、軽トラックの助手席へと移っていく。
(ヤバい、見つかる)
その時だった。 キャリーバッグの中から、シズクが不安そうに
「ミャ」と、小さく鳴いた。
「……!」 終わった、と思った。
大家さんの眉が、吊り上がる。
「……今の音、なん……」
「――緊急地震速報です!!」
私のスマホが、けたたましいアラーム音で鳴り響いた。 大家さんも、私も、肩をビクッと震わせる。 一瞬の静寂。
「……なんだい、驚かせるね! 地震かい!」
大家さんの意識が、完全にスマホのアラームに移った。 (……揺れ、ない?) 不思議に思いながらも、私はこのチャンスを逃さなかった。
「す、すみません! 急いでやりますので! 騒がしくして、本当に申し訳ありませんでした!」
私は頭を下げ、冷蔵庫を無理やり荷台に押し込んだ。
大家さんは
「まったく、最近の若い者は……」
とブツブツ言いながらも、地震速報の余韻(結局、それは誤報だった)に気を取られ、部屋に戻っていった。
私は、崩れ落ちそうになる膝を叱咤し、助手席のドアを開けた。 キャリーの中では、シズクが、私のアラームが鳴る直前に鳴いたきり、静かに座っていた。
「……シズク、あんた……」
偶然? 本当に、ただの偶然だったのだろうか? あの「ミャ」という鳴き声は、まるで、私のスマホに「今だ」と合図を送ったかのようだった。
=================
3.
新しい部屋は、がらんどうだった。 埼玉県の△△駅。 オートロックといっても、暗証番号式の簡素なもの。六畳一間のワンルーム。 築25年とあって、フローリングには無数の傷があり、壁紙も少し黄ばんでいる。
けれど、私にとっては、城だった。
『第二さくら荘』から運び込んだ、わずかな荷物を部屋に放り込み、私は床に大の字になった。 汗と埃で、身体中がベタベタだった。 残高、七万。 体力、ゼロ。
(……私、本当に、何やってるんだろう)
虚しさが、疲労と共に押し寄せてくる。 私は、この子猫一匹のために、すべてを捨てた。 安定した家賃。なけなしの貯金。明日への余裕。
その時、ペチ、ペチ、と小さな足音がした。 キャリーバッグから出てきたシズクが、恐る恐る、新しい部屋の匂いを嗅ぎまわっている。 そして、床で伸びている私のところまでやってくると、私の頬を、ザラザラした小さな舌で、ぺろり、と舐めた。
「……!」
くすぐったくて、温かい。 私は、思わず笑っていた。
「……あはは。そっか。一人じゃ、ないんだよね」
私は起き上がり、シズクを抱きしめた。
「ここが、私たちの家だよ」
シズクは、私の腕の中で「ニャア」と答えた。
荷解きは、まだ終わらない。 けれど、窓から差し込む西日が、この傷だらけのフローリングを、とても優しく照らしているように見えた。
=================
4.
新生活が始まって、一週間。 私の日常は、様変わりした。 通勤時間は、片道1時間半から、2時間10分になった。毎朝5時半に起きなければ、会社に間に合わない。 食事は、自炊が基本。特売のモヤシと豆腐。たまに買う鶏むね肉が、ごちそうだった。 残高は、5万円台になっていた。
生活は、間違いなく苦しくなった。 けれど、不思議なことに、心は、あの『第二さくら荘』にいた時よりも、ずっと軽かった。
「ただいま、シズク」
「ニャア(おかえり)」
暗い部屋のドアを開けた時、私を迎えてくれる、琥珀色の瞳がある。 それだけで、2時間10分の満員電車も、耐えられた。
シズクは、やはり不思議な猫だった。 私が落ち込んでいると、必ず膝に乗ってきて、ゴロゴロと喉を鳴らす。 私が仕事の愚痴をこぼすと、「ミャウ」と相槌を打つように鳴く。 そして、あの夜のような不思議な光は、あれ以来、一度も見ていない。 (やっぱり、夢だったのかな) (地震速報も、偶然だった) そう思い始めた頃、それは起きた。
=================
5.
金曜日の夜だった。 疲労困憊で帰宅すると、会社のグループチャットが赤く点滅していた。 開いた瞬間、心臓が凍った。 上司からの、全体メンション。
『――例年の、秋季デザインコンペだが、今年はウチの部署から、橘さん。君にメインでやってもらうことにした。期待している』
(……なんで)
指先が、震え出した。 デザインコンペ。 それは、私の「過去の影」そのものだった。
私は、今の部署に配属される前、デザイン部にいた。 二年目、同じコンペで、私は大きなミスを犯した。 クライアントの意向を読み違え、まったく方向性の違うデザインを提出。プレゼンは惨敗。部署は大きなチャンスを失い、私は「使えない」というレッテルを貼られ、今の(誰でもできる)事務処理の部署に、事実上、左遷された。
あの日以来、私は「デザイン」から逃げてきた。 新しいアイデアを考えること。 自分の作品を人前に出すこと。 それが、怖かった。
『橘さん、返事は?』
上司からの、追い打ちのメッセージ。
(無理) (また失敗する) (期待している、なんて、皮肉だ)
息が、苦しくなる。 あの雨の夜、バスの中で感じた虚無感が、何倍にもなって私を飲み込もうとしていた。 私はノートパソコンを閉じ、ベッドに倒れ込んだ。 「……もう、やだ……」
涙が、じわりと滲む。 その時だった。
「……ミャア」
シズクが、ベッドに飛び乗ってきた。 そして、うずくまる私の顔を、じっと覗き込んできた。 あの、琥珀色の瞳。 夜の部屋で、それはランプのように、静かに、強く光っていた。
「……シズク……私、ダメなんだ……」
「また、失敗するの、怖い……」
シズクは、私の涙を気にするでもなく、ベッドを降りた。 そして、部屋の隅、引っ越しの荷物でまだ雑然としている、段ボールの一群に向かった。 そこには、私がデザイン部時代に使っていた、古い資料やスケッチブックが詰め込まれていた。 捨てられなかった、「過去の影」の残骸だ。
シズクは、その段ボールの一つに飛び乗ると、前足で器用に蓋を開け、中から一冊の古いスケッチブックを、引きずり出した。
「……え? それ……」
それは、私が二年前に、あのコンペで惨敗した時の、アイデアスケッチブックだった。 シズクは、そのスケッチブックを、私の枕元まで引きずってくると、その上に、ちょこんと座った。
「……ダメだよ、シズク。そんな古いの……」
私が手を伸ばし、それを取り上げようとした。
「フシャァッ!!」
シズクが、初めて私に向かって、威嚇の声を上げた。 鋭い爪が、一瞬だけ、光った。
「……!」
私は、驚いて手を引っ込めた。 シズクは、私を威嚇した後、再びスケッチブックの上に座り直した。 そして、私をじっと見つめる。 琥珀色の瞳。
(……この瞳、だ)
あの夜、パソコンを見ていた時と同じ、真剣な瞳。 私は、まるで催眠術にでもかかったように、シズクの瞳に引き込まれていった。 琥珀色の奥深く。 そこには、宇宙のような、深い闇と、無数の光が渦巻いていた。
――琥珀色の瞳が、私の「過去の影」を見つめている。
次の瞬間、私の脳裏に、あの惨敗したプレゼンの記憶が、鮮やかに蘇った。 クライアントの冷たい視線。 上司の失望した顔。 自分のデザインの、どこがダメだったのか。 逃げ出したくて、目を背けていた、あの記憶。
(……やめて)
そう思ったのに、シズクは、私から目を離さない。 まるで、「見ろ」と、「直視しろ」と、無言で命じているかのように。
=================
6.
どれくらい、そうしていただろう。 数秒か、あるいは数十分か。 シズクの瞳を通して、私は、自分の「失敗」のすべてを、もう一度、体験した。 涙が、止まらなかった。 後悔と、自己嫌悪と、恐怖。
だが、すべてを見終わった時。 不思議なことに、私の心は、嵐が過ぎ去った後のように、静かになっていた。
「……そうか」
私は、呟いていた。 「……私、あの時、諦めたんだ」 クライアントの意向を読み違えたんじゃない。 最初の修正指示でパニックになって、自分の「やりたいこと」を全部捨てて、相手の顔色だけを伺った、中途半端なデザインを出した。 だから、ダメだったんだ。
シズクが、私の顔をペロリと舐めた。 もう、威嚇はしていない。
「……ありがとう、シズク」
私は、シズクが座っていたスケッチブックを、そっと手に取った。 シズクの温もりが、まだ残っている。
パラパラと、ページをめくる。 そこには、惨敗したデザインと、その前に描いていた、ボツにしたラフスケッチが残っていた。 今、冷静な目で見ると、そのボツにしたラフスケッチは、荒削りだが、確かな「光」を持っていた。
(……これだ) (あの時、私が捨てたアイデア)
シズクは、私がこの「種」を、自分自身で見つけるまで、私の「過去の影」に、一緒に座っていてくれたのだ。
私は、ベッドから跳ね起きた。 そして、埃をかぶっていたノートパソコンを、勢いよく開いた。 上司へのチャットに、返信を打つ。
『コンペの件、承知いたしました。やらせてください』
震えは、もう止まっていた。 残高、5万円。 通勤、2時間10分。 それでも、私の心は、今、なけなしの貯金を全額持っていた時よりも、ずっと豊かだった。
私は、新しいページを開き、ペンを走らせた。 あのラフスケッチを、今の私で、もう一度。 隣では、シズクが、満足そうに喉を鳴らす音がしていた。
第四話へ続く・・・
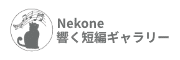


“【短編小説全10話】第三話:琥珀色の瞳が見つめる、過去の影” に対して1件のコメントがあります。